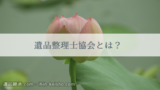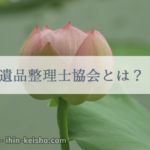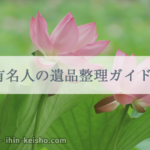遺品整理をスムーズに進めるには、専門知識を持った人のサポートが欠かせません。この記事では、遺品整理における重要な資格「遺品整理士」について、仕事内容や資格の取り方などをわかりやすく解説します。
- 「遺品整理士」の資格と仕事内容がわかる
- 資格取得の流れと必要な費用について理解できる
- 遺品整理士が提供できる具体的なサービスを知ることができる

「遺品整理士」ってどんな資格でどんな仕事をしているんですか?

「遺品整理」関連のサイトによく出てくる「遺品整理士」について詳しく調べてみました。
「遺品整理」を調べていると、よく目にする「遺品整理士」ってどんな資格でどんな人が取得しているのだろう?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。今回は
「遺品整理士」という資格について
を調べてみました。
「遺品整理士」はどんな資格で、どこが発行しているのか。そして、具体的に何ができるのか。そうした疑問を解消するための情報をこの記事でお届けします。
「遺品整理士」は、遺品整理を専門的にサポートするための資格です。
信頼できる業者としての認定を受けることで、遺族の負担を軽減しながら、適切な整理を行う手助けができます。
遺品整理に必要な資格
遺品整理を頼むなら、業者がどんな資格を持っているか気になりませんか?
遺品整理には、さまざまな法的要件が関わる場面があります。不用品の回収や処分、物品の売買を行う場合、「一般廃棄物収集運搬業」や「古物商」といった資格や免許が必要です。
古物商は売買に関する資格ですが、遺品整理士は遺族の気持ちに寄り添いながら整理を進める専門資格です。
一方で、「遺品整理」そのものに関する国の免許や国家資格は存在しません。そのため、心ない業者によるトラブルが後を絶たず、信頼性のある認定資格が求められるようになりました。
無資格業者による不法投棄や不適切な処分が報じられることもあり、遺族が予期せぬトラブルに巻き込まれるケースもあります。このような問題を防ぐためには、信頼できる資格を持つ業者に依頼することが重要です。
無資格の業者が不法投棄を行い、それが発覚して遺族に罰金が科されたケースといったトラブルは、業者が法律や規制を十分に理解していないことが原因で起こります。
遺族にとっては想定外の負担となり、大きな問題に発展することも少なくありません。
ここで注目されるのが「遺品整理士」という民間資格です。この資格は、安心できるサービスを提供し、遺族の負担を軽減することを目的としています。
あなたは、遺品整理を任せる業者が本当に信頼できるか、考えたことがありますか?
次のセクションでは、「遺品整理士」とはどのような資格で、どのように取得できるのか、またどのように活躍しているかをご紹介します。
遺品整理士とは
遺品整理士とは、遺品整理に特化した専門知識を持つ民間資格です。この資格は、一般社団法人 遺品整理士認定協会が発行しており、遺族の負担を軽減し、適切な整理をサポートすることを目的としています。
- 遺族の心理的負担を軽減
一人では難しい遺品整理をサポートし、安心感を提供します。 - 不法投棄などのトラブルを防止
法律に基づいた適切な整理を行います。 - 安心して任せられる専門家
遺族の意向や故人の意思を反映した整理が可能です。
この資格を持ったスタッフがいれば、思い出の品や形見分けの品を丁寧に分類してくれたり、家族の想いや故人の遺志を反映した整理ができると、近年人気が急増しています。
一般社団法人 遺品整理士認定協会は、遺品整理士の育成を目的に、講座の運営や資格発行を行っています。また、遺品整理士の活動支援、業界全体のルール整備、最新情報の提供など、遺品整理を取り巻く環境の健全化にも取り組んでいます。
さらに詳しくは
をご覧ください。
次のセクションでは、この資格の取得方法や費用について詳しく解説します。
遺品整理士になるには
遺品整理士になるためには、遺品整理士認定協会が実施する通信講座で「遺品整理士養成講座」を受講することが必要です。
「遺品整理士認定協会」へ電話するか公式サイトから申し込めます。教材は教本、問題集、資料集、DVDになり、問題集に沿って課題レポートを提出します。内容は遺品整理に必要な正しい知識と処理方法の他、廃棄物やリサイクル品の取り扱いに関する法規制なども含まれます。
- 公式サイトまたは電話で申し込み
- 教材を使い課題レポートを作成
- 修了後、認定証が発行される
講座を修了して課題を提出し合格すると、認定証書が発行され「遺品整理士認定協会」に加盟することができます。
合格認定がされるまで、おおよその目安として2ヶ月とされていますが、無料で期間延長も可能です。受講の際に実務経験は必要なく誰でも受講できますが、反社会勢力に該当する方は受講ができません。
合格率は70%で、そこまで難しくはないようです。
次に、この資格を取得するための費用について詳しく見ていきましょう。
遺品整理士取得にかかる料金
「遺品整理士認定協会」公式サイトによると、
入会金・テキスト一式送料は会費に含まれております。
「遺品整理士認定協会」公式サイト
その他、資格認定時の年会費(資格認定会費)、資格の年度更新として、年会費(更新費2年間有効)をお支払いいただきます。
年会費(資格認定会費・更新費)は、7,000円(2年間有効)となります。
尚、年会費(資格認定会費・更新費)は、クレジット決済が出来ませんのでご了承ください。
「遺品整理士」及び「遺品査定士」の資格認定について、年会費(更新費)をお支払いいただいていない会員様は、「遺品整理士」「遺品査定士」の名称を使用した活動を行うことができませんので、あらかじめご理解をお願いいたします。
とのことでした。
遺品整理士ができること
遺品整理士は、遺族の負担を軽減する専門家です。遺族が一人では整理できなかった遺品を丁寧に分類し、家族の希望に沿った形で形見分けを進めます。
また、不用品を適切に処分し、故人の思いを大切にした整理を行うことで、「心の整理ができた」と感謝されるケースも多くあります。
遺品整理士の役割を理解したところで、次にどのような場面で必要とされるか見ていきましょう。
どういう時に遺品整理士が必要とされる?
かつては、故人の部屋の片付けは遺族が行うものでした。
しかし現在では核家族化や共働きのライフスタイルが一般的となり、遺品整理を遺族だけで行うのは負担が大きく、時間的にも難しくなってきています。
さらに高齢者だけの世帯も増え、体力的に遺産整理が難しいケースもあります。
よって共働き世帯や高齢者世帯からの需要が多いです。
その他、疎遠となっている親類が孤独死した場合にも依頼が多い傾向です。
遺品整理士を頼むことで、遺族の負担が大きく軽減されるケースがあります。
- 心理的負担の軽減
故人に関連する品々を一人で整理するのは辛い作業ですが、遺品整理士のサポートにより、スムーズに進められたという声が多くあります。 - 物理的負担の軽減
高齢の遺族や多忙な家族にとって、遺品整理士が提供する清掃や分類、搬出のサポートは大きな助けとなります。 - 効率的な整理
プロの手を借りることで、価値ある品を見落とさずに整理が進められます。
こうした状況に直面した場合、遺品整理士の力を借りると安心です
遺品整理士は単なる片付けのサポートだけでなく、遺族に安心感と満足感を提供する存在となっています。
遺品整理を業務とする事業者
遺品整理では清掃・運搬・リサイクルといった作業が発生します。
そこで「清掃会社」「運搬会社」「リサイクル業者」などが遺品整理事業を事業拡大の副業としておこなっています。
現在はそういった業界が各々「遺品整理士」の資格を取得しはじめており、遺品整理の業界全体の健全化が図られはじめているといった状況です。
さらに詳しくは
をご覧ください。
信頼できる業者の基準
遺品整理を任せる際に、業者が本当に信頼できるかを見極めるために、以下の点に注目してください
- 法令遵守
遺品整理に必要な「古物商許可」や「一般廃棄物収集運搬業許可」を取得しているか確認しましょう。これらの許可がない業者は、適切な処分が難しい場合があります。 - 認定資格の保有
「遺品整理士」などの資格を持つ業者は、専門知識があり、遺族に寄り添った対応が可能です。 - 口コミや評価
過去の依頼者からのレビューを参考にすると、業者の信頼性が把握できます。 - 透明な料金体系
事前に見積もりを提示し、不明瞭な追加料金が発生しない業者を選びましょう。
これらの基準を満たす業者を選ぶことで、安心して遺品整理を任せられるでしょう。
遺族の思いを大切にしながら進める業者を選ぶことが心の整理にもつながり、結果的にトラブルを防ぐ第一歩となります。

どういった目的で作られた資格なのかがわかったかと思います。
まとめ
いかがでしたか?今回は、
「遺品整理士」という資格について
を調べてみました。
急増する「遺品整理」のニーズにこたえトラブルを減らすために、必要とされ誕生した資格だということがわかりました。
資格保有者を選ぶことで、安心して整理を任せられます。
遺品整理士が遺族の負担軽減にどれほど役立つかを理解できたのではないでしょうか。
この記事があなたの「遺品整理」のお役に立てたら嬉しいです。